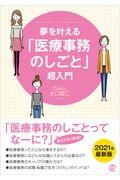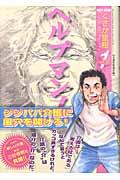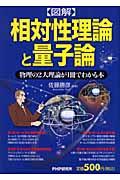推薦図書(専門書)
※本のタイトルをクリックするとオンラインブックストアにリンクしています。

『スポーツの仕事大全-45人のスポーツプロフェッショナルたち-』
プロスポーツ選手やコーチのみならず、スポーツマネジメント、医療、研究者など、スポーツに関わる様々な仕事が紹介されています。また現場で働く方々のインタビューが掲載されていることから、やりがいや苦労など、より具体的に仕事内容を理解することができます。将来、スポーツ業界で仕事をしたいと考えている学生にとって、未来の可能性を広げる一冊となるでしょう。
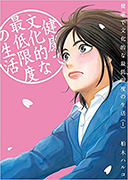
この本では、今の福祉的課題、ソーシャルワークの成り立ち、福祉の国家資格、実践、これからの展望などが、語られています。どんな社会を目指し、ソーシャルワーカーとはどのような存在であるべきかを考えさせられます。
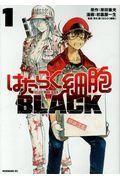
人々の生活上の課題やそれに対応し人々の暮らしを支えるソーシャルワークが学べます。イラストや福祉課題に関連するデータも掲載されていて、ソーシャルワークに関心がある方々にお勧めの1冊です。

著者は、人気お笑いコンビ「メイプル超合金」の安藤なつさん。実は、介護現場歴20年という介護現場の大先輩でもあります。自身の介護経験や、介護現場で活躍する人の取材など、介護の仕事とその魅力をわかりやすく紹介されています。

2018年にはテレビドラマ化もされ話題になりました。社会人1年目の主人公が、生活保護のケースワーカーとして、様々な困難を抱える生活保護受給者の人生に向き合い、奮闘、成長していく物語です。
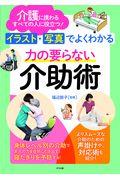
『ヘルプマン!』
マンガを通して介護職の現場・家族介護の現状を知ることができます。介護を行っている・見たことがある方は「介護において大切なことは何か」を考える機会となり、介護の現場を見たことがない方は「作者や主人公から介護がどう映って見えるのか」が知ることができます。
推薦図書(一般書)
※本のタイトルをクリックするとオンラインブックストアにリンクしています。

目まぐるしく変化する現代社会において、如何にしてその状況の変化に対応するのか、また過去に縋らず、どのようにすれば常に新たな自己の可能性に向かって生きれるのかついての指針が示されています。2人の小人と2匹のネズミがチーズを探していくという物語なので非常に読みやすいです。興味がある方は、読んでみてください。

著者の東田直樹さんは、重度の自閉症です。この本では、「大きな声はなぜ出るのですか?」「どうして目を見て話さないのですか?」など、質問に答えるかたちで、自閉症に対する理解が深まるようにと東田さんが自閉症の人の心の中を説明しています。

『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと』
ボルネオ島の狩猟採集民「プナン」とのフィールドワークから見えてくる「豊かさ、自由、幸せとは何か」を根っこから問い直す、刺激に満ちた人類学エッセイです。

生き方を紐解くヒントが散りばめられた一冊。自由な思考と行動によって生まれる成長と満足感が魅力的でもあり、我が人生における存在価値と心豊かな人生への鍵を見つける旅となるでしょう。
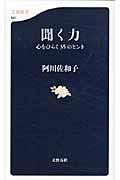
長きにわたり愛された世界名作劇場のアニメシリーズ、かつて子供だった頃に見ていたアニメの世界に心を揺り振り戻される名言の数々が集められた本です。今の皆さんにぴったりな言葉が見つかるかもしれません。


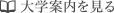
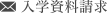



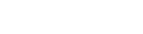
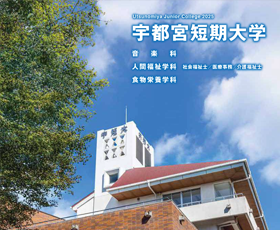 ▲オープンキャンパス・大学祭のご案内
▲オープンキャンパス・大学祭のご案内 ▲音楽科オープンキャンパス実技レッスン
▲音楽科オープンキャンパス実技レッスン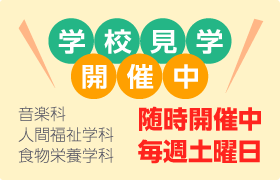 ▲学校見学会~校舎を実際に見学して、宇都宮短期大学をより身近に感じてください。
▲学校見学会~校舎を実際に見学して、宇都宮短期大学をより身近に感じてください。